
新幹線に乗るとこどもが乗り物酔いするのだけれど、いい対策法はないかしら?
乗っていれば目的地へ高速で連れて行ってくれる新幹線。渋滞もなく、ほぼ時間通りに運行する、とっても便利でありがたい乗り物ですが、乗り物酔いをする人にとっては乗車するのがつらい時間でもあります。
乗り物酔いしない人にとっては、「新幹線で酔うの?」と疑問に思う方も少なくないかもしれません。
しかし、新幹線でも酔う原因があり、とくに東海道新幹線のN700系は酔いやすいとされています。
我が家の娘もN700系で酔いました…。
こちらの記事では、新幹線で酔う原因と新幹線酔いの対策方法を特集します。
記事をチェックして、次に新幹線に乗る際のご参考にしていただけると幸いです。
\おススメの酔い止めリストバンド/
新幹線で乗り物酔いする原因
新幹線で酔う原因はいくつかあげられますが、主な原因は以下のとおり。
- 目で見る情報と体感のズレ
- 気圧による影響
- 電磁波による影響
- 寝不足などの要因
新幹線酔いする原因は、他の乗り物と同じような原因もありますが、新幹線特有の原因もあります。それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。
新幹線酔いの原因1 目で見る情報と体感のズレ

一般的に、“乗り物酔い”をする原因の一つに、目で見た視覚の情報と、体が感じる体感のズレがあげられます。
目で見た景色の情報と三半規管に伝わった揺れの情報などは、前庭小脳に集められます。
様々な情報が絶えず伝わることで脳が疲労し、混乱をおこして自律神経が乱れます。この自律神経の乱れが乗り物酔いの症状となってあらわれます。
新幹線は高速で移動するため、外の景色が猛スピードで流れていきますね。日常生活では感じないスピードの視覚情報なので、とくに疲労を感じやすいです。
新幹線酔いの原因2 気圧による影響

新幹線では、他の車両とすれ違う時やトンネルを出入りする時に、高速で通過するために一時的に気圧の変化が生じます。
この気圧の急激な変化は、三半規管などの内耳にも大きな負担になりますし、自律神経もストレスを感じます。
日頃から天気の変化による気圧差に敏感な人は、特に注意です。
新幹線酔いの原因3 電磁波による影響

乗り物酔いをしなくても、「新幹線に乗ると疲れる。」というかたもいらっしゃるのではないでしょうか。
もしかしたら、それは“電磁波”によるものかもしれません。
新幹線の車内は、走行中に電磁波が高くなります。東海道新幹線のぞみの窓側は、瞬間的に300ミリガウス(安全数値の300倍)もの電磁波を測定するという情報もありました。
新幹線酔いの原因の一つに“電磁波”による影響も少なからずあるのではないかと思います。
新幹線酔いの原因4 寝不足や空腹などの要因
普段、乗り物酔いをしない大人でも、寝不足や空腹などの要因がそろえば乗り物酔いをしやすくなります。
新幹線に乗る前には、体調を整えておくことは大事です。
乗り物酔いをしやすい新幹線は『N700系』
一言で新幹線と言っても、様々な種類があり、車体によって乗り物酔いをしやすいものがあります。
とくに乗り物酔いをしやすいと言われているのが、東海道新幹線などで使われている『N700系』です。

原因は『空気ばね式車体傾斜システム』によるもの
なぜ、N700系の新幹線が酔いやすいかというと、車体に『空気ばね式車体傾斜システム』という装置を搭載しているから。
カーブを曲がる際に、台車上に設置された左右の空気ばねの伸縮差によってわずかに車体を傾斜させます。すると、従来よりも速度を落とさずにカーブを通過することができます。
カーブの多い東海道新幹線で、超過密なダイヤを運行させるために、新幹線として初めて採用されました。
なぜ、空気ばね式車体傾斜システムが乗り物酔いを引き起こすかというと、低周波振動によって独特な左右の揺れをおこし、その揺れが乗り物酔いをしやすくしてるのではないかと言われています。
なるべく乗り物酔いをしにくい新幹線に乗りたいですよね。空気ばね式車体傾斜システムを搭載しているかは、次の項目でチェックしてみてください!
空気ばね式車体傾斜システムを搭載する新幹線の確認方法
乗り物酔いをしやすい人は、なるべく空気ばね式車体傾斜システムを搭載した新幹線を避けた方が賢明です。
空気ばね式車体傾斜システムを搭載している新幹線は、以下のとおり。
N700系(16両編成の東海道新幹線、山陽新幹線)

N700S(東海道・山陽新幹線の一部、西九州新幹線)


E5系(「はやぶさ」の全列車、「はやて」「やまびこ」「なすの」の一部)

E6系(「こまち」の全列車、「はやぶさ」「やまびこ」「なすの」の一部列車)

新幹線の乗り物酔い対策方法
上記のような乗り物酔いをしやすい新幹線を知っていても、どうしても乗らなくてはいけない場合があります。
そのような場面でも、なるべく乗り物酔いをしにくくする対策方法はいくつかありますので、事前に心得ておくだけでもだいぶ違います。ぜひチェックして対策してみることをおススメします。
乗り心地が向上した最新のN700Sを選ぶ

東海道・山陽新幹線の一部や、西九州新幹線には、最新のN700Sという車両が採用されています。
フルモデルチェンジした最新のN700Sは、揺れを打ち消す仕組みのフルアクティブ制振制御装置というものが搭載されており、乗り心地がよくなっています。
搭載されている場所は、グリーン車、揺れが強い先頭車両&最後尾、パンタグラフを備える5号車&12号車です。
東海道新幹線に乗る場合、N700Sを選ぶと従来の車両よりも酔いにくいかもしれませんね。
チェックするには下のボタンをクリック(タップ)してください!
乗り物酔いしやすい人は車両の真ん中&通路側がおすすめ

車両の真ん中や、通路側の席は、他の座席に比べて揺れが少ないです。
電磁波の強さも、窓側の数値が高く、通路側の座席は他に比べて数値が低くなっています。車両の入り口付近ではなく、真ん中あたりの席がベスト。
窓ガラスは特に電磁波が強いので、もたれかかったりするのは避けた方がよいです!
また、先頭と最後尾の号車は揺れが強いので、なるべく避けたほうがよいですね。
- 先頭&最後尾以外の車両
- 車両の真ん中あたり
- 通路側の席
ゲーム機や携帯の画面&本を見ない
長距離の移動では、こどもが飽きてしまうため、ついついゲーム機やスマホを使わせてしまったり、本を読ませてしまいがちですが、乗り物酔いしやすい方にとっては新幹線乗車中のこれらの使用はNGなんです。
先に書いた乗り物酔いの原因の一つに“目で見た視覚の情報と体が感じる体感のズレ”がありました。
ゲームやスマホの画面を見たり、本を読んだりすると、視線が固定されます。体は新幹線の揺れで常に動いているのに、視線は固定されている状態は、自律神経が乱れ、まさに乗り物酔いをしやすい状況になります。
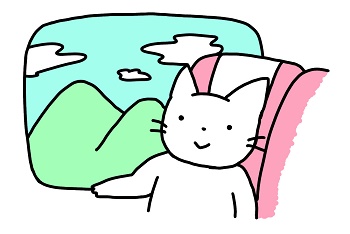
乗車中は、窓の外の景色をぼんやり眺めるなどをして、ゆったりと座って過ごすとよいと言われています。
景色をガン見してしまうと、視線が定まって酔いやすくなりますので、あくまでも“ぼんやり”眺めるのがコツです。
長時間の乗車だと、窓をボーっと見るだけではお子さんがジッとしているのがつらい場合がありますよね。そんな時は、シール遊びがついた電車の本がおススメ。クイズやちえあそびなど電車尽くしの一冊です。
乗り心地のよいグリーン車を利用する

グリーン車は、揺れが少なく、一番快適に乗れるように設定されています。
東海道新幹線で言うと、16車両の8,9,10号車がグリーン車になっているように、揺れの少ない真ん中に位置していますね。
もし、お金をプラスしても快適に乗りたいという方は、グリーン車を利用してみてはいかがでしょうか。
乗車前に体調を整えておく
寝不足や空腹&満腹だと、酔いやすくなります。
まずは、新幹線に乗る前に、なるべく酔いにくい体調にしておくとよいですね。
お子さんの乗り物酔い対策は、以下の記事でまとめました。詳しく書いてありますので、よろしければご参考になさってください。
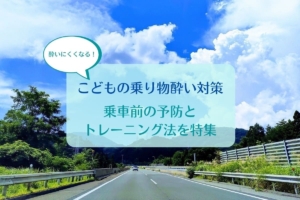
手軽にできる新幹線酔い対策グッズを活用する
事前に体調を整えたり、なるべ酔いにくい席を選ぶのはもちろんですが、“乗り物酔い対策”できるアイテムを用意しておくと、さらに心強い味方になるのでおススメです。
酔い止めバンド

新幹線酔いには、薬に頼らなくとも手首につけるだけで乗り物酔い対策ができるリストバンド型の酔い止めがおススメ。
手首のツボを刺激し、乗り物酔いの不快感を和らげるものです。
我が家の娘は峠道でのドライブに効果抜群でした!
詳しくは、こちらの記事で書きましたので、合わせてご参考になさってください。

酔い止めドロップ

NEXCO西日本のSA・PAを中心に販売が開始され、今や全国の高速道路のSA・PAやフェリー、JR東日本のコンビニ「ニューデイズ」などでも取り扱いされている、大人気の「酔い止めドロップ」。
主成分がアスコルビン酸(ビタミンC)ですので、薬が苦手な方でも摂取しやすいですね。
万が一のお守りとしてカバンに忍ばせておくと心強いです!
まとめ
新幹線の乗り物酔い対策は以下のとおりです。
- 乗り物酔いをしやすい新幹線&席を知っておき、なるべく避ける
- 体調を整えておく
- ゲームやスマホ、読書などをしない
- お金に余裕のある時はなるべくグリーン車を利用する
- 乗り物酔い対策のグッズを使う
対策を知っておいて、実践してみることで、何も対策をしない時よりもグンと乗り物酔いしにくくなりますし、何よりも気持ちに余裕が出るのがよいですね。
ぜひご活用してみてください!




